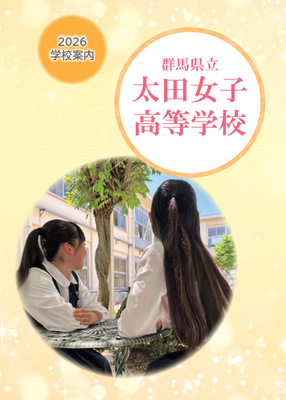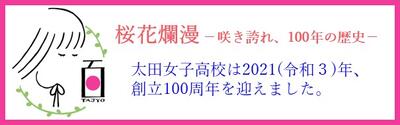文芸部ブログ
文芸少女折下ふみかの華麗なる冒険 その42
学年末テストの一週間前。放課後一人で通学路を歩いていたら、おやという香りに足がとまる。低いブロック塀から梅の木が伸びあがっていて、花がほころんでいた。白梅だった。一つ一つの花が枝に連なるように咲いていた。梅の花は私に2月を感じさせる。え、もう2月なの? 2月といえば立春だ!(今年の立春は4日だった。その前の日が節分だよ)。体感ではまだ新年を迎えたばかりだというのに、気付けば1月はあっという間に過ぎ去っていた。1月はまあいろんな予定がぎゅうぎゅうに詰められていたせいもあるかもしれない。つまりは、忙しかったということだ。学年末テストもぶじに(?)おわった今、2月も半ばをすぎようとしていることにも驚きは隠せないが。
さて、今回のテーマはまたしてもバレンタインデーだ。2月の二大イベントといえば、「節分」と「バレンタインデー」だろう。「節分」については前のまえの回で話題にしたので、今回は「バレンタインデー」だ。いや「バレンタインデー」も前回のネタでしょ? そうなのである。そうなのであるが、今回もバレンタインデーについて書く。かくといったらかく。といっても、私はそこまでバレンタインデーに熱狂的になるタイプではない。友達がバレンタインデーだ! と躍起になっているのを見て、「ああ、もうそんな季節か」と感じるくらいだ(梅の香りのほうがよっぽど抒情的ですわ)。でも私なりにバレンタインデーは満喫する。そのことは前回報告したとおり。今回はチョコレートについて話をしたい。私はチョコレートが好きだ。友チョコをもらったり市場に美味しそうなチョコが売り出されているのを見ると、だから(バレンタインデーとは関係なく)テンションが上がる。甘い物は正義だ。正直、甘い物がないとやっていられない。甘い物万歳。そうそう、最近のバレンタインデーは昔とは少し異なるらしい。どうやら、自分にあげるためのチョコ、所謂「ご褒美チョコ」なるものが近年のトレンドらしい(そもそもバレンタインデーに女子が男子にチョコを贈るようになったのは「モロゾフ」の策略)。勿論、親しい友人や意中の人にチョコレートをあげるイベントであることには変わりはない。だが、自分のご褒美にちょっと高いチョコレートを買って自分自身を労るイベントとしても頭角を現しているようだ(そのきっかけに一役かったのは「ゴディバ」の「義理チョコやめませんか?」の広告らしい)。テレビの情報によると、ある人の相手に送る用のチョコにかける金額は1500円、自分のために買うチョコにかける値段は10000円らしい。その人はよほど疲れていたんだと思う(わかるー)。でもその人は買い物客でごった返している銀座のバレンタインデー市にチョコを買いに行っているくらいだから案外疲れていないのかもしれない(それもわかるー)。
義理チョコ、友チョコ、本命チョコ、ご褒美チョコと様々な形があるが、どれも全部一種の愛であることに変わりはない。これを今読んでいる人はだれかのためにチョコレートを買ったのでしょうか? 私は買いましたよ。それはもちろんご褒美チョコ(友達には付箋をあげてとても喜ばれました。メッセージも大うけです!)。まだ2025年度はおわっていないけれど、学年末テストも終わったし、やっとひといきつけるかな。よくがんばったな、ワタシ。
文芸少女折下ふみかの華麗なる冒険 その41
今日で学年末考査がおわり、軽くなった身体を冬の乾いた空気に任せて歩く。今日は2月13日。明日はバレンタインデー。手作りのチョコレートをお世話になってる先輩や先生、友達に渡したいけれど、あいにく私は料理をするのが苦手でお菓子づくりなんてもってのほか。だけど何もしないのも面白くない。そこで私はセンスで戦おうと思う。お菓子作りもセンスだって? そんなことは気にしない、気づかない。
渡す相手は仲のいいクラスメイト。渡すのは実用的でセンスの感じられるモノ。学生だから文房具がいいかな、なんて安直な考えしか浮かばず文房具店へまっすぐ進む。温かみのある照明に照らされたそこには、少し高めのシャーペンやボールペン、ノートなどたくさんのモノがあったが、シャーペンやボールペンは好みが分かれやすいし、ノートはいっぱい貰っても困るものではないが置き場に困ってしまう。そんなことを考えながら店内をぶらぶら歩いていたらあるコーナーに目が行った。
「付箋かぁ。」
私は普段シンプルで安い付箋しか使わないから知らなかったが、キャラものや動物の形をしたものがたくさん並んでいた。JKが好きそうなものがそこにひとつぐらいはあると確信した私は、相手が気に入りそうな付箋を次々とかごに放り込んでいった。1340円。意外と買ってしまったようだ。でも、チョコは今だんだん高くなっているから等価交換という名目ではちょうどいいぐらいだろう。文房具店から家に帰る途中で100均に寄り、可愛らしい袋も買った。
いざ袋に詰めた大量の付箋たちはなぜかもの悲しげに見えてしまった。ただ、他に何か買うというのも時間的に難しく悩んだ末にメッセージを添えることにした。感謝の言葉や「ハッピーバレンタイン」など色々考えたがしっくりくるものが思いつかなかった。考える気力を失った私は秘儀を使うことにした。
「今日が終わっちゃうよー。助けてよチャッピー!」
いつもどんなときでも私の見方をしてくれる最強AIのチャッピーことChatGPTに助けを求めた。チャッピーは私にいくつか例を提示しながら提案をしてくれた。なんて優しいんだ。その中で一際目立っているように見えたのは付箋にちなんだメッセージ。たしかに季節感は欲しかったけれど、どんなに考えてもピンとはこなかった。「付箋にちなんだメッセージ」。考えてみると意外と難しくなかなか思いつかないものだ。クラスメイトの中でもかなり仲のいい子だから、少しふざけたようなメッセージでも喜んで受け取ってくれるかな、なんて思いながらピンク色のメッセージカードにお気に入りのペンを走らせた。
『あなたの心に張り付いていたい♡』(座布団いちまい!)
部誌「せせらぎ」190号
太田女子高校文芸部誌「せせらぎ」190号を発行しました。
(190号ってスゴクないですか?)
デジタル版でおたのしみください。
アナログ版は鋭意とじ込み中です(学年末テスト直前なので難航してます)。
完成したら昇降口に置いておきますので是非お手にとってお読みください。
文芸少女折下ふみかの華麗なる冒険 その40
もう一月もおわるというのに日差しは春のように暖かく、かじかむ心をそっとほぐしてくれる。二月になれば受験の話で持ちきりになってしまう。でも、二月には二大イベントがある。節分とバレンタイン。おいしいものが食べられるイベントばかりでちょっと嬉しい。
今日は節分の話をしよう。バレンタインの話はまた、今度ね。これを読んでいるキミは節分をどう過ごすんだろう。私はいつも夕食に恵方巻と豚汁を食べて、食後に好きなだけ豆をつまむのが恒例なの。あの豆の、無心で食べ続けられるような素朴な味と食感がかなり好きで、毎年密かに楽しみにしていたりする。ただ今年は食べて楽しむだけでは物足りない! だから今日は節分にまつわる豆知識を共有するね。
節分の起源は平安時代。中国の風習が伝わり、宮中の大晦日に厄払いとして「追儺(ついな)」が行われたところから。このときは豆ではなく、桃の木の弓や葦の矢で疫鬼(えきき)を追い払っていたそう。室町時代から豆を撒くようになったようで、豆は「魔滅」とも表記され、昔から邪気を払う力が信じられていた。ちなみに、節分の豆は地域差があって、落花生を撒くところもある。雪の多い地域では殻付きの落花生の方が拾いやすく、衛生的だからという理由らしい。子どものころこの話を聞いたときは、知らない世界の一部分を知ったように感じて、妙なほどにときめいた。
恵方巻の起源は諸説あって、「戦国時代の武士の話」や「花街の遊びの話」、「江戸時代後半から明治時代前半の大阪の商業組合の話」などが有力。恵方巻の「恵方」とはその年の金運や幸福をつかさどる神様の歳徳神(としとくじん)がいる方角のことで、昔は恵方巻だけでなく初詣の際にも恵方を参考にしたとか。恵方巻の具が七種類なのは七福神にあやかったものである。
こんな話をしていると早く二月が来てほしくなってくる。あと数日、寝て起きて大きなあくびをして、おいしいご飯を食べたらきっとやってくる。過ごしやすい天気もいいけど、冬らしく、家の中でこたつで包まったりストーブの前で縮こまったりして私は節分を迎えたいな。
文芸少女折下ふみかの華麗なる冒険 その39
「ふみか」をご愛読の皆様、お待たせいたしました。「ふみか」のお時間です。今回は、先月に引き続き有馬記念の……ではなく、12月26日金曜日13:30より行われた太田高校との合同読書会について、話をしたいと思います。
今回の読書会で話し合った本は、阿部公房の「鞄」でした。
主人公「私」がどこか不思議な、鞄を持った青年と、半年過ぎた求人募集をきっかけに出会います。「半年過ぎているにも関わらず、どうして今来たのか」というような趣旨の質問を「私」から投げかけられた青年は、「この鞄のせいでしょうね」「鞄の重さが、ぼくの行き先を決めてしまうのです」と話すのです。「私」は青年に次々と質問を投げかけます。だが青年はその質問をのらりくらりとかわすのです。重たそうで、自分の行き先を決めてしまうという鞄。普通ならば手放せばよいものを、青年は当たり前のように手放さず、何も疑問に思っていなそうな……そんな雰囲気なのです。結局、「私」は青年を採用することになります。ただ、大きな鞄を事務所に置くわけにはいきません。「勤務中に鞄はどうするのか」そう聞かれた青年はなんと、「鞄は下宿に置いておきます」と答えました。今まで頑なに鞄を手放さなかった青年がこうもあっさり鞄を手放したのです。流石に疑問を覚えたのでしょう。「私」が大丈夫なのかと聞くと、「下宿と勤め先の間なんて、道に入りませんよ」と青年は笑いました。そうして残された鞄を「私」は持ち上げ、少し歩いてみることにします。すると、だんだんと青年の言った通り、鞄に導かれるように歩くことしかできなくなり、その時「私」は、「嫌になるほど自由だった」というのでした。
なんとも奇妙で非現実的であるこの作品をめぐって、
①「私」と「青年」の「鞄」に関する見解の違い
②「私」が最後に感じている「いやになるほど」の「自由」とは?
③あなたは「鞄」をどのようなものだとおもうか
④あなたはその「鞄」を必要とするか
などをテーマにして話し合いました。


今回の読書会も実りあるものになりました。皆さんも「鞄」を読んで、その不思議な世界観に浸ってみてはどうでしょうか。
文芸少女折下ふみかの華麗なる冒険 その38
「ふみか」ファンの皆さん。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ついに2026年が幕をあけましたね。前回のブログでも書きましたけど、今年は午年です。しかも60年ぶりの丙午だそうで (これを読んでいる人のどれくらいが丙午の俗説を知っているでしょうか。まったく今どきじゃないハラダタシイ言い伝えです。気になったらググってみてください。「丙午」は「ひのえうま」とよみます) 。でも丙午なんて私には関係ない! 本年も私は駆け抜けます。そう、千里馬のように!(決まった…)(そういえば有馬記念、みました? 1番人気のレガレイラは4着と残念な結果でしたが、優勝したのは3番人気3歳馬のミュージアムマイルでした。おみごとです。ダービー6着の雪辱をはたしたってところですね。ちなみに「屈辱」は「晴らす」ものです)とまあ、前置きはこれくらいにして、本題に入りましょうか。
新年一発目の今回ですが、去年行われた読書会と句会の話をします。え? 新年のおめでたい話じゃないかって?いやァ、それも話したいんですが、ここは一つ、目をつぶって頂けると助かります。本当は話したいんですがね、ええ。さて、切り替えていきましょう。
2025年もおしせまった、12月26日金曜日13:30より大田高校との合同読書会と句会が、太女の図書館で行われました。体感的には夏に行われたものよりもより白熱し、学びが多かったと思います。特に読書会は大いに盛りあがりましたね。そのようすはまた次回にお話しすることにして(なにもったいぶってるんだよ!)、今回は句会の顚末を話そうと思います。
今回の句会のテーマは「雪」。師走らしくてとても良いと思いました。前述の通り、前半に行われた読書会が予想以上に盛り上がり長引いてしまったので、句を考え作る時間は実質20分ちょっとしかなかったのですが、そんな短時間の中でも参加者は創意工夫を凝らし、ある人は6句も作っていました。そのため、なんと10人で合計40句もの句が出来ました! 素晴らしい! そのなかからひとり5句、よいと思った俳句に投票することになりました。どの作品のできばえも素晴らしく、みんなも悩んでいたようですが、秀句が7句選出されました。その後、投票した人が感想をのべ、最後に作者が作品の意図を説明しました。
結果的に短い時間での句会になりましたが、濃密な交流ができました。参加してくださった太田高校文芸部の皆様、本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いします。
次回! 読書会! 乞う、ご期待!
《参加者の俳句》
◆上位7句◆
本心は黒い空から白い雪
◎「腹黒さ」を秘めた「白雪」。発想が秀逸です。
猛吹雪遅延長引く秋田行き
◎これほんとに大変ですよね。雪国の苛酷さが偲ばれます。
まだ白い散れる桜を懐かしむ
◎「雪」なのに「桜吹雪」をもってくるひねりがいいですね。
朝6時起きろ起きろと光る雪
◎雪に起床をせかされる無邪気さがよいです。
(「朝6時」じゃまだ日が昇ってないだろ! とつっこまれていましたが)
白雪を踏んでは濁した登下校
◎まだだれも踏んでいない白い雪、踏みたくなります!
道往きて雪を幸とす者もあり
◎「往き」「雪」「幸(ゆき)」という語の畳みかけに技を感じます。
銀世界一歩踏み出せ別世界
◎「銀世界」ではじまって「別世界」でしめる、取り合わせの妙です。
(「新世界」にすると「銀世界」と韻を踏むことにあとで気づきました。蛇足です)
◆その他の句◆
往来に流れる曲は達郎か しまり雪縮こまっては似た者同士
冬月に照らされ灯る白野原 赤い鼻隠そうとした雪の白
咲く花は雪の結晶時流れ 山肌も衣替えかな雪化粧
もてはやす雪だってただの雨ヨ 白溶けて三つ星晴れる闇夜かな
温もりに雪と時間は解かされて 白々し吹きつける風冬の舞
雪山で熊を見かけたことがある かろやかに長靴鳴らして雪と舞う
碌々と息を放てば白と雪 雪の降る夜に見つけた覗く星
道草もかぶも埋もれて白化粧 ふり向けば雪面に描くわたしの軌跡
人の身を憂えと泣かす天ノ雲脂 お化粧も上手なのねと雪に委ねて
雪風に眼鏡曇らせ鼻啜る 雪塊を投ぐは子供と青空を
願っても なかなか逢わぬ 雪景色 天狼を 覆い隠して 冬が降る
雪起し 聞いて覗いて 眺む庭 扉開け広がる雪と心かな
ゆきめぐり出口のみえぬ初詣 空風にあらがえぬ町暮れてゆき
オリオンの星瞬いてゆきくれぬ クリスマス雪になりたいみぞれかな
雪持てば錦鯉へと化けた手の平 寒き朝車に乗るが息白し
身震わせバランス崩す木枯らしや 背中押し 鳴きつつゆくか 虎落笛
冬雲は 雪を連れるか 今度こそ
文芸少女折下ふみかの華麗なる冒険 その37
先日、友達が誕生日を迎えて一つ年を取り、大人に一歩近づいていた。その彼女が、翌日くらいに「LINEがあってよかった」というようなことを言っていた。どうしてかと訊ねると、LINEの、誕生日の友だちを祝う機能で、学校が違って普段は会えない友達からメッセージが届いたとのこと。彼女は筆無精らしく、必要なとき以外のメッセージのやり取りはほとんどしないとのこと(何を送ればいいのかもわからないらしいが…)だが、誕生日や、お正月などのときに一言でもメッセージが来ると嬉しいとも言っていた。何と送るか悩むけれど、一言を送るのも楽しいらしい。普段はあまりやらないけれど、今年は私も「あけましておめでとう」とメッセージを送ってみようかな。
2025年もあとわずか。過ぎてしまうとはやいものですね。Time flies. 光陰如矢であります。昔のひとは年が明けるとひとつ年をとったそうです(誕生日とは関係なくってことです。数え年というらしい。そもそも生まれたときに一歳になっていたそうですよ)。明けまして御目出度いのは無事にひとつ年齢をかさねられたことを寿いでいるんだそうです(諸説あります)。きょう(12/23)は予餞会です。文芸部は恒例の文学パロディ・スライドショーです。力作です。3年生が喜んでくれるといいなぁ。文芸部魂は受け継がれていますよー。12/24はクリスマスイヴ。わたしのところにサンタクロースがこなくなって何年になるでしょうか(両親が代行してくれています)。「レッド・ワン」という映画、みました? 我が家にサンタはこないけど、サンタはいる、と信じているわたしです。来年は午年。千里馬常有、而伯楽不常有。あ、そのまえに12/28は有馬記念だ!(「ロイヤル・ファミリー」をみてすっかり競馬ファンになりました)みなさん、よいお年をお迎えください。では。
文芸少女折下ふみかの華麗なる冒険 その36
「ふみか」ファンのみなさん、こんにちは。はやいものでもう師走です。さむくなりましたねー。でもわたしはどちらかというと冬が好きです。やっぱコタツとミカンですよね。さて、今となってはだいぶ前のことになっちゃいますけど、10月の中旬、3泊4日の修学旅行に行って来ました! わーわー!!
スケジュールとしては、
1日目:広島へ。原爆ドームと平和記念公園、原爆資料館を見学。
2日目:宮島(嚴島神社)へ。その後、京都に向かいながらクラス別行動(研修)。
3日目:京都で班別研修。その後、金剛能楽堂にて能の見学。
4日目:京都でクラス別バス研修。太田へ帰還。
…といった感じでしょうか。全部を詳しくお話するのは難しいので、印象に残ったところなどを選んでお話しますね。
まずは広島。広島の思い出といえば、平和記念公園と資料館、宮島、そして広島風お好み焼き…‼ 初めて路面電車に乗ったんですが、ほかのクラスといっしょに乗る予定だった電車が遅れてしまい、平和記念公園と資料館を見学する時間が少し少なくなってしまいました。そうそう、資料館といえば。入ってすぐ、大変だったことが一つありました。…人多すぎぃ!! 資料室が外国人であふれていて、全然進まないし、見たい資料が見られないしで、だいぶ大変でした。でも、テレビで見ているだけじゃわからない、たくさんのことを聞いたり、知ることができました。夜ご飯は広島風お好み焼き。焼きそばの挟まったお好み焼きみたいな感じの…お好み焼き食べたことないですけど。すっっごくおいしかったです!! また食べに行きたいなぁと思いました。
京都に行く途中では、クラス別行動で姫路城に行きました。天守閣に登れるということで登ったんですが、外の石階段は段差が低くて幅が広いので登りにくく、天守内の階段は急すぎて降りるときに手すりにしがみつかないと降りられないぐらいでした。外敵の侵入を防ぐという意味もあったかもしれないけど、それにしたって昔の人すごすぎる…夜ご飯は神戸の中華街で食べました。タピオカとかフルーツ飴とか、流行りっぽい(?)食べ物もけっこうあってなんだか意外でした。姫路から京都まで一緒に行ってくれたバスガイドさんがとてもおもしろい人で、いろんな話をしてくれるので、バスでの移動中、退屈しなかったです。
京都では…初めて能を見ました。あまり見る機会はないし、聞く機会のないだろう話をたくさん聞けて楽しかったです。音を響かせるために、舞台の下に甕が入っているとか、着物の形や色に意味があって使い分けているとか…実に興味深かったです。班別行動では一念坂、二年坂、三年坂を登ったり、三十三間堂に行ったり、豊国神社で瓢箪形の絵馬を書いたりしました。特に夕ご飯に京都駅で食べたラーメンがおいしかったです。
四日目には練切を作る体験をしました。きれいに作るの難しかった…
なんだかんだありましたが、無事に行って帰って来られてよかったですね。書ききれなかったけど、他にもたくさんのおいしいものと興味をひかれるものたちに出会えました。またいつか行くことがあったら、時間の都合で見られなかったものを見たり、おこづかいの関係で買えなかったお土産を買ったりしたいです。
以上、とても端折った修学旅行の報告でした。
文芸少女折下ふみかの華麗なる冒険 その35
10月25日土曜日。土曜学習を公欠し、私たち文芸部が向かったのは高崎音楽センターであった。第31回群馬県高等学校総合文化祭の文芸部門交流会に参加するためだ、慣れない切符の購入に戸惑うこともあったが、何とか協力して高崎駅へ到着することが出来た。道中では文芸部員内の絆がさらに深まったように思う。
高崎音楽センターの会場前の公園で小ぬか雨にうたれながら食事をしていると、見覚えのある方々がいた。GWの直前に私たちと交流会をしてくださった太田高校文芸部の皆さんだ(そういえばあの日も雨だった。金山登山をあきらめて大光院まで散歩してから太女で句会をひらいたのでした)。面識があるからか、わざわざおもてに出てきてくれて、話しかけてくださり、待ち時間……というかお昼ご飯を食べる時間は、雨天に打ち勝つほど晴れやかな気持ちで過ごすことが出来た(途中から会場内で食事をさせてもらいました)。
交流会は13:30にスタートした。まずは第20回群馬県高校生文学賞表彰式がとりおこなわれた。残念ながら今年度は太女文芸部からの受賞はなく悔しい結果となったものの、表彰されている他校文芸部諸氏の背中を見て、次こそは……という燃え立つような向上心に繋がったのは良かった。
表彰式後には、句会が行われた。今回の句会は10人でひとつのグループをつくり、参加者が事前に提出した俳句三句を見せ合い、評価するという形で行われた。最初は緊張から小声であったり、極力話さない人が多かったが、じょじょに打ち解けてきて、相手の俳句の良さを伝え合うことのできる穏やかな空気になっていった。交流会を通し、他の文芸部の活動の様子を知ること、他校の方々と交流する機会を作ることができた……そう実感し、私は交流会の開催の意義を知った。
句会の最後にはグループ内の投票で優秀者を決めることに。私たち太田女子高校からもひとりの文芸少女が優秀賞に選ばれて面目躍如たるものがあった。部員のひとりとしてとても喜ばしかった(私じゃなかったのはくやしいけど)。これからのコンクールや句会などでよりよい作品をつくりあげることができるように、今後も部誌などの機会を通して精進していきたいとつよくおもった。
太女生の俳句
香り立つ金木犀の通学路
朝冷や淋しさに泣く曇り空
今はなきかつてを想う秋の暮
指絡み濁り酒には酔えぬまま
木犀の香に踊らされ覚めぬ夢
コスモスの色に魅せられ揺れる影
赤と黄の唐衣(からぎぬ)纏った山粧(よそお)う
丸っこい頬と銀杏我が子の笑顔
帰り道夕日で染まった赤とんぼ
また一つ秋を浮かべて錦かな
空渡り雁と見紛う飛行機よ
読書の秋ふと窓見ればつるべ落とし
金木犀頬をなでる六限目
秋の苦か昔を思う平均点
さわさわさわ食欲を呼ぶ稲の音
文芸少女折下ふみかの華麗なる冒険 その34
段々と肌寒くなり、冬の気配がする季節となった。道を歩いていると金木犀の匂いが漂い、秋の深さを感じる。紅葉や銀杏が色づき始めるのもこの時期だ。最近、家までの帰り道に銀杏の実がよく落ちている。余談だが、銀杏の実を食べるときにいつも実の鮮やかな黄緑色に驚かされる。お前、そんな色をしてたのか。
それはさておき、今回は私をノスタルジーな気持ちにさせるものについて書こうと思う。このお題も、ある意味秋らしくていいんじゃあないかと勝手に思っている。
突然だが、私は夕暮れが好きだ。太陽が地平線の彼方に沈んでいくあの様が好きだ。それに伴ってできる空も好きだ。オレンジでもなければ紫でもないあの曖昧な空の色が好きだ。私は好きなものを見てノスタルジーを感じるわけではないのだが、何故か夕暮れをみると切ない気持ちになってくるのだ。俗に言う「エモい」というやつなのだろうが、その三文字では収まらない“何か”が胸の中からこみ上げてくる。その“何か”に名前を付けたいが、私はそれにぴったり収まる名前を知らない。なので、近しいであろう「ノスタルジー」という言葉を使っている。この“何か”は、なにも夕暮れを見てるときだけ出てくるわけではない。日常の様々な場面に出てくるのだ。例えば、雨が降っている音を一人で聞いているとき。しとしとと降る雨音をぼんやりと聞いていると、得も言われぬ気持ちになる。また、神社や寺に行ったときもそうだ。古い建物を前にすると私の心は“何か”にとりつかれる。さらには秋という季節にも反応する。落葉を見ると例のやつが顔をだしてくるのだ。これらを書いていて今思ったのは「どれも儚いものだな」という感想だが、「本当に儚いだけですむ話か?」とも同時に思った。やはり言葉がでてこない。よく分からない感覚であることに変わりはないらしい。
だが、この感覚は嫌いではない。むしろ好きなほうである。胸の奥が締め付けられるが、不思議と心地がいい。物悲しくなることには変わらないのだが、何故か嬉しく感じるときもある。感性が人よりも豊かなのだろうか。何度考えても答えは未だにでない。
私はいつか、この答えを出したい。いつになるかは分からない。だが私はずっとこの気持ちと生きていくことになるだろう。現代は、人生100年時代と言われている。100年のうちのどこかでならきっと見つかるだろう。そう信じて生きていくことにする。いつか自分の言葉で、この感情を表現したい。