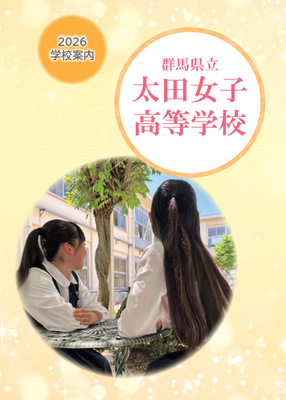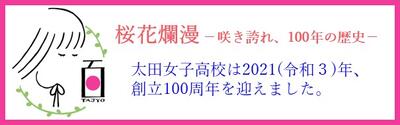文芸少女折下ふみかの華麗なる冒険 その28
今年度のメンバー全員が揃った状態での、最初で最後の部誌『せせらぎ』189号が先日発行されました。ほんらいなら「創作余話」というカタチで本誌に載せたかった、作者の作品への思い入れやこだわりを集めました。みんなそれぞれにさまざまな視点や発想で創作しているんだなぁと改めてつくづく思い知らされます。合評の記事と合わせてお読みくださいませ。
なお、ネタバレを含む可能性もありますので、本誌をお読みいただいてからの閲覧をお勧めします。
『ずっと、大好きだから』銀平糖
この話を書いているとき、子供の視点で書くのは初めてだったので、新鮮な感じがしました。悲しいことがあっても、前向きに生きていこうとする子供がもつ明るさや前向きさを表現しました。
『神様になった少年の話』ラギ
大好きな先輩方の引退号となる、ということで、現在の自分に出せる全力を尽くして最高のものを書こうと密かに決めていました。花言葉や色の表現など、とことんこだわりました。とある推しの二次創作から着想を得たネタの、ifのifを出す予定で書いていましたが、途中で書けなくなってしまうハプニング(いつものこと)が起こってしまい、急遽予定を変更してifの話を書き上げました。想定外だったのは、登場人物が語り手の一人を除き、全員元ネタの人にそっくりになってしまったことです。元ネタがいる分、いつもよりキャラがしっかり定まったと思っていたんですが…ちょっと個性が強すぎたようです。もう一つは、一人が視点&語り役に徹した結果、名前くらいしかわからない謎の人物になってしまったことです。自分は気に入ったんですが、元ネタの人が口調にしか残っていないという…結果的には視点専用のキャラクター、という新たな試みとなりましたが。
補足:人名にふりがなを振ったんですが、一人抜けていました。「八朔日」は「ほずみ」と読みます。
『返事のない星』神樂坂
今回の小説が部誌に載る一作品目となる、肝心ですがどんなものがいいのか分からず書き始めました。今回の自分のテーマの「生きること」と「変化」を中心に、自分の経験したことのない遠距離の二人の関係を書きました。ぎこちない文になっていると思いますが、様々な視点から読んで楽しんでいただけると幸いです。
『身代わり姫と傀儡王』阿野二枡
引退作となりますので、執筆中はこれまでよりも背筋の伸びる思いでした。登場人物の名前や地の文の言葉に、読む方によっては実在の人物や舞台作品を連想させるものがあるかもしれませんが、色々な資料のごった煮から考えたので、特定の一作品・一史実の二次創作ではありません。主人公たちには、時代や運命に翻弄されながらも与えられた役割の中で懸命に生き、最後は幸せを掴んで報われてほしいと思いながら書きました。ヴィッツェルはヴィッテルスバッハ(バイエルンの名門貴族)、シエルージュはフランス語のCiel(「空」から「青」を連想して)+Rouge(赤)から採ったほか、普通に読んでも差し支えないものの、分かると少し面白いかもしれない言葉遊びが散りばめてあります。
『愛しい悪夢の中で』あきつさ
部活を引退するにあたって部誌に載せる最後の作品となるので、自分の好きな要素、書きたいこと、全部詰め込みました! 過去に囚われてしまう主人公は、きっと他人事ではないと思っています。苦しい中でも救いとなるような友人と出会えたら、それは一生物の宝だと思います。以下、入れようとしたけれど登場人物に却下されたセリフ。
(笑い声が響き渡る夢の中で)
「今ここで一発芸したらさ、どれだけつまんなくても大ウケしてるみたいだよね」
「……絶対にやめてね」
『思い出のお城』銀平糖
私が市の図書館で勉強していたとき、おじいさんが司書さんに「アメリカの地図を出してほしい。ハーストキャッスルを探したいんだ」と言っていたのが、この物語を書き始めたきっかけです。(←決して会話を盗み聞きしようと思ったのではなく、おじいさんの声が響いていたので、自然と耳に入ったんです)作者としては、読んでくれた方が少しでも楽しい気持ちになってくれたら、と思っています。
『おかえり』幻想翡翠
このせせらぎに初めて小説を載せるにあたって、活動場所であるコンピュータ室から見えた山から着想を得ました。とにかく神経質で、近寄りがたいけれど「静寂」という彼女には人一倍愛を注ぐ、どこか歪な彼の独白をどうぞ見守って頂けると幸いです。
『一蓮托生』みみず
部誌「せせらぎ」に初参加の私。今回の部誌でスタートダッシュがどう切れるかが、創作活動への自信やこれからの活動のモチベーションになる……そう考え、思い切って自らの好きを曝け出すことに決めました。とある高校生二人が抱える、懺悔と希望、そして歪な形の愛とそんな二人の結末とを、是非最後まで見守ってくれたらと思っています。
◆顧問からひとこと◆
毎度のことながら部員ひとりひとりの創作意欲に圧倒されます。高校生のわたしにこれほどの小説はかけなった(なにしろ処女作は大学1年生のときかいた400字詰め原稿用紙5枚の作品ですから)。表現力も構想力も素晴らしいものがあります。よみごたえじゅうぶんです。それぞれにスタイルをもちあわせていて(もちろんそれが個々人でも多様なんですが)次回作への期待を抱かせてくれます。せっかくなので個別に(「おとな」の立場から)助言らしきものをかいてみます。「阿野二枡」氏のかく作品のタイプはそもそも分量を要求します。丁寧に物語をつみあげて緻密にねりあげてゆけばもっともっと素晴らしい作品を生み出せるでしょう。「あきつさ」氏はある意味ダークファンタジーめいたものを確立しています。それをもっと大きな物語にできるとおもしろいですね。わたしは短篇しかかけないんですけどあなたには長篇を期待したいってことです。「ラギ」氏はおそらくあふれるものがおおすぎて自分で制御できていない状態だとおもいます。かくまえにプロットを練りあげる必要がある。発想はよいのでそれを生かしましょう。「銀平糖」氏は身辺雑記的なんだけれどそこにちょっと日常を逸脱したウイットめいたものが見え隠れする作品をかきます。「ずっと好きだから」はぼかしすぎましたかね。図書館でのエピソードから「思い出のお城」にいたる脳内変換はだれにもまねできません。ほとんど体験談じゃないのに展開の自然さがすばらしいです。1年生は(ごめんなさい、ひとまとめにします)はじめてとはおもえない力作ぞろいです。でもやはりはじめてなりに共通した「はじめて」らしさに満ちています。それは観念的な作品になりすぎているってところです。モチーフが心情的なものであり、そのことだけをぐいぐい押してくる傾向がつよい。作品の中心はそれでいいんですけど、それをもっと物語でおおいかくす工夫があるといい(と、わたしはおもいます)。次回作は展開にこだわってみましょう。