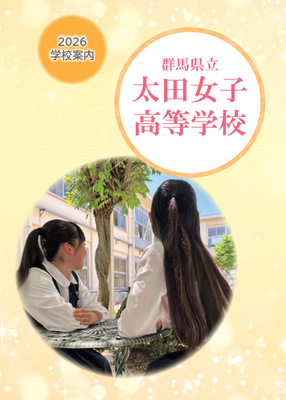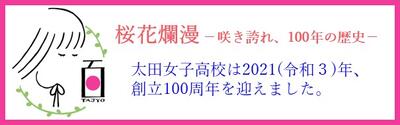文芸少女折下ふみかの華麗なる冒険 その25
7月23日水曜日、夏季前期課外がおわった酷暑の午後、学校の図書館に集まって、「せせらぎ」189号の合評会を行いました。

今回は、一年生にとって初めての「せせらぎ」でした。ですが一年生は臆することなく、自らの作品作りに真剣に向き合い、自分の思いを込めた個性ある物語を形成していました。二、三年生の作品は表現や登場人物の設定に深みがあり、一年生はその作品を見て先輩との差に焦る気持ちや、数年後にそんな深みと工夫の込められた文を作り上げられるようになりたいという憧れを感じることになりました。
合評会は共感や賞賛の声が行き交い、とても良い雰囲気で行うことが出来ました。また、その中にはアドバイスも多く、気軽にアドバイスをし合える所で、この文芸部の仲の良さや信頼を感じることも出来ました。
やはり「せせらぎ」を発行するだけではなく、合評会を開き文章の真意や工夫を共有し合うことで、お互いを高め合うことや仲を深めることに繋がり、よりよい作品作りをすることが出来るのだなと感じました。次回の「せせらぎ」発行時も、このような有意義な時間を過ごせたらと思っています。また、今回の合評会で学んだことを文章に活かせたら良いなとも考えています。
以下にしるすのは、作者のこだわりや作品の感想をまとめたものです。ネタバレの塊なので、まずは「せせらぎ」189号に目をとおしてからこちらお読みくださいませ。なお「せせらぎ」189号は「文芸少女折下ふみかの華麗なる冒険その23」に掲載されています。
「ずっと、大好きだから」
主人公は学校にもまだ通っていない小さな女の子。子どもから見た家族の様子は難しくて、ママの入院のこともお葬式のこともよくわかっていないけれど、それでも新しい母親がママではないことがわかっている、そんな話。
「神様になった少年の話」
主人公は、神様になった少年とかつての友人たちをひとつにつなげる役割を持って物語を回しているんだ。登場人物の選んだお供え物の花の花言葉にまでこだわりがあって、カタクリは「寂しさに耐える」、黄色の水仙は「私のもとに帰って」、ハナニラは「悲しい別れ」、ネリネは「また会う日を楽しみに」、白百合は死者への捧げ物。未来への希望はあるけれど、すこし悲しい話。
「返事のない星」
ヒト、ニンゲン、とカタカナを使うことで主人公の人見知りな性格を表現している。たくさんの食べ物の描写をいれることで、食べることは生きることだから主人公たちが生きていることを表している。季節を表す表現を多く取り入れて、読者が主人公たちの感じる感覚を共有できるようになっている。
「身代わり姫と傀儡王」
史実をもとに考えた作品。史実ではすべてが悲劇に終わってしまったから、幸せな物語として書き上げた。登場する二つの国の元ネタの国に合わせた言語ベースで名付けていたり、長めの話だけれど内容を短く章ごとに区切っていて読みやすかったりと、中世ヨーロッパの雰囲気を楽しみやすい作品。
「愛しい悪夢の中で」
主人公は過去のトラウマから眠るたびに悪夢を見ている。そんな彼女が友人と夢の中でも会い、ほんの少しだけ悪夢を恐れなくなる話。人は誰しも多かれ少なかれ心に傷があって、他の人に傷を晒したりはしないが、それでも気づいてくれる友人との出会いが救いになる。
「思い出のお城」
昔に見た白いお城をもう一度見てみたいというおじいさんと、いったいどのお城のことなんだろうと考えるおばあさんの話。歳をとっても仲が良く、孫たちとも一緒に映画を見るような関係を築けていて、とてもほのぼのとした世界が形作られている。
「おかえり」
なによりも静寂を愛する主人公が、むかし美術館や図書館で会った「彼女」を探し求めてひとり山を登る物語。騒がしいことが嫌いな主人公が耳を澄ませてでも必死に「彼女」を探す姿勢には彼の執着とも言える愛が見える。彼が愛したのは「静寂そのもの」だった。
「一蓮托生」
一蓮托生は、もとは仏教用語で「死後に極楽浄土に生まれ変わったときに同じ蓮の葉の上に生まれ変わること」。転じて良いことも悪いことも運命をともにすること。最期に二人が進んでいった夜の海は、生き残ろうと足掻けば助かることだってできた場所。それでも進んでいった二人の覚悟と、互いへの愛情が表されている。